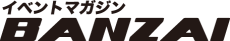日本を代表する演歌歌手 “北島三郎” が歩んできたプロとしての道のりとは
1962年にデビューして『なみだ船』のヒットによって脚光を浴び、『兄弟仁義』『帰ろかな』『函館の女』『与作』『風雪ながれ旅』などを歌って、常にトップ・スターとして活躍を続けてきた北島三郎。歌を愛し、歌とともに生きて55年、人は彼を「演歌の大御所」と呼ぶ。しかし、それだけで本当の姿をとらえたことにはならない。プロデューサー、作詞作曲家、舞台作家などとしても仕事をしてきた北島三郎から、プロフェッショナルの流儀を語っていただいた。

魂が入ればいい声が出る
──北島三郎さんは昨年、芸道55周年を迎えられました。長きにわたりステージに立ち続けてきた方として、思うところや考えを伺いたいと思います。
まず、舞台に上がり歌を聴いていただく者としては、いつも来てくださったお客様に魂を込めた歌を届けるだけではなく、お土産に持って帰れるものは何かということを考えていますね。「あの話で泣かされた」とか「あのセットがきれいですごかった」とか、ご来場いただいたお客様には歌はもちろんそれ以上のお土産を持って帰ってもらわないといけない。われわれは夢や希望を与える職業をしてご飯を食べさせてもらっているんですから。そういう気持ちを忘れずにやっているから55年も経ったけれども、神様からまだ歌の道を歩かせてもらえているのかもしれないと思います。
──北島さんが歩んでこられた、この55年は現代の舞台芸術が発展してきた歴史そのものでもありますよね。東京では、日本武道館でビートルズの公演を行うようになり、中野サンプラザなどの会場でもコンサートが開かれるようになりました。その中で北島さんは活躍を続けてきたわけです。
シミズオクトさんとはお互いに長いこと頑張って来ましたね(笑)。例えば新宿コマ劇場での公演の最初のころ、どうしても舞台で雨を降らせたい場面があって、当時はそんなことを誰もやっていなかったので劇場からは「床下に電気が通っているので水は難しいです」と言われたんだけど、シミズさんに相談をして挑戦したんです。本番の舞台では、次第に役者たちが濡れていくのを見て「あれ!?」とびっくりしているお客様がいたり、水しぶきがかかって「本物の雨だ!」と喜んでいたり、そのお客様の反応に自分たちも感激するんです。いろんな人の力を借りて舞台に立たせていただける訳ですし、お客様はお金を払い時間をかけて足を運んでくださっている。だから、ただ出ていって歌っているだけじゃダメなんです。舞台のすべてを使ってお客様に来てよかったと思われるものを作らないと。

──どうすれば観客の心に届けることができるか ?それを考えたのはいつごろからですか?
デビューする前の演歌師の時代から夜の裏町で勉強してきたんですが、聴いていただいた方々の思い出をよみがえらせたり、歌の内容に共感してもらえたりする歌がいい歌、心に届く歌であってそれにはきれいに歌うとか大きな声を出そうとか、そういう余計なことは要らないんです。ただ、自分らしく精一杯の心を込めて歌う。そうすると「いやぁ、涙が出てきちゃった」なんて言葉が返ってくる。そういう声を聞くと、「あぁ、俺の歌はこの人の心に届いたんだな」と思えて、次はもっと満足してもらえるように、そうやって今日まで歌ってきたんですね。
──上京当時、クラシックの音楽学校にも通われていたんですよね?
そうですね。学校で覚えたこともありますよ。例えばイタリア人歌手のテノールはなんであんな声が出るんだろうと思って、ひと月発声法を勉強したら声がよく響くようになった。喋る声も響いた方がいいと思って、まず鼻に響かせよう上顎に声を当てようなんていうことも工夫しながらやったんです。しかし、いい声で歌えば感動してもらえるかと言ったら、声だけじゃ感動してくれない。すごく上手にコブシを回してみても、やっぱり感動してもらえない。何が足りないのかって考えると、まず歌詞がある。歌詞があって、それが何を訴えているかを考えて、それで聴いてくださる方が情景を思い浮かべたり、自分の歩いてきた道を思い出したりしてくれたら、感動してもらえるんですね。だから、上手く歌おうとか、いい声で歌おうとか、あんまり考えないようにしています(笑)。でも、ここぞという時には、プロとしていい声を出さなきゃいけない時もある。そういう時は魂を入れればいい声が出るんです。
──魂が入るとは ?
魂が入るとか入らないとかは説明するのが難しいんだけど、自分がいろんな歌を聴いて感じてきたものがあるから、それが手本になっているのかな。黒人歌手のブルースなんてね、虐げられた人たちの心の叫びみたいなものを感じるし。日本の演歌歌手“北島三郎”は世界に一人しかいない歌手なんだから、自分自身で精一杯、魂を込めて歌おうと思ってやってきたら、あっという間に80歳を過ぎました(笑)。
──長年歌手としてだけでなく、プロデューサー的な立場からステージをつくってこられましたが、大切にしていることはありますか?
ものをつくるには、実際に現場に立って周りのスタッフや客席の皆さんとぶつかり合った方がわかることがたくさんあるんですよ。旅をすれば、東海道の松は真っすぐだけど、日本海の松は横に伸びているなんていう違いがわかる。歌だって場所が変われば、歌い方も表現も違うものになる。
そういう、現場でこそわかるもの、その場にいるからこそ学べるものが大事なんですね。おかげさまでたくさんの舞台に立たせていただいてきましたから、勉強もたくさんさせてもらえました。一日に何千人というお客様が見て「すごいねー」って言ってくれる舞台をつくるには、関係者や裏方の皆さんのどれほどの苦心や努力があるか。そして、心から「よかった」と言ってもらうためには、細かいところにまで気を配っていなければいけないという基本。舞台に立つわれわれアーティストだけでは仕事はできない。
現場を大事にして、ちょっとしたこともおろそかにしないシミズさんのようなスタッフやブレーンとスクラムを組みながら、今日まで歩かせてもらえていることには本当に感謝しています。
新しくて面白いと思えるものを生んでいってほしい
──デビューしたころと比べて、メディアもテレビ中心とになり、様々なジャンルの若いアーティストも出てきました。
昔は公開放送をするといってもラジオですから、目を閉じていても風景が描けるようになんて考えて歌っていたわけです。それが、聴かせるのと同時に観せる時代に変わりましたよね。衣装も演出も華やかになって、振り付けなんかも派手になってくる。そうすると私たちが歌ってきたような演歌は、イメージがちょっと暗いんですね。
最近の『紅白歌合戦』なんかでは若い人が大勢で踊りながら歌うようなものと、われわれのような演歌が同じ枠に収まることになって、ワーッと盛り上がった後に一人でしんみり歌うことになる。そうするとどこか寂しいんですね。それぞれコーナーを分けるとか、もう少しやり方があるんじゃないかと思うんですが(笑)。いずれにしろ今の若いアーティストの中にも素晴らしい才能の持ち主がいるし、いい歌もいっぱいありますよ。自分としてはそんな彼らはライバルだと思いますから、負けずに頑張らないといけないなと思ってます(笑)。
──豊かな経験があればこそのお話の数々、こちらもとても勉強になります。おしまいに読者の皆さんへ言葉をいただけたらと思うのですが。
特に若い人に言いたいのは、いろいろなことに興味や好奇心を持ってほしいということですね。世の中が便利になって世界中が近くなったから、昔は見られなかった国を観たり聴けなかった音楽を聴いたりできるようになったでしょう。そういう時代に生まれ育って、小さい時からいろいろな音やリズムに囲まれてきているから、音楽について言えばものすごく自由で発達していると思う。パターンにとらわれないで、感じたままにやれるじゃないですか。だから、今の人たちには自分たちが持っている環境や才能を生かして、音楽でも何でもどんどん新しくて面白いと思えるものを生んでいってほしいと思いますね。
とは言っても昭和の時代のものにも大事なことはたくさんあるので、それが描かれた演歌の灯りも消しちゃいけない、せめて自分が生きている間は灯しておこうと私はそう思ってこれからも歩み続けていきます。
新作CD

夢千里 (ゆめせんり)
日本クラウン CRCN-3612 ¥1,204(税別) 発売中