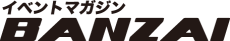仕事の流儀 音楽評論家 湯川れい子
音楽を愛し、音楽に愛されて……。音楽評論家、作詞家、翻訳家、ラジオDJなど、多岐に渡って活動を行っている湯川れい子さん。彼女が先駆者として、これまで切り開いてきた道のりとは——。

好きな音楽を聴くことができる環境は宝物だと思います
——いろいろな活動をされているなかで、代表的なお仕事である音楽評論家を始めるきっかけは何でしたか?
「戦後はロックンロールが日本に入ってくる前にジャズブームがあって、私は高校生の時にモダンジャズにはまりこんでいまして。高校を卒業する頃に日本でもアート・ブレイキー&ザ・ジャズ・メッセンジャーズとかホレス・シルヴァーなどを中心に、ファンキージャズというのが盛り上がって、流行の最先端の音楽として騒がれるようになった時に、ちょっと違うんじゃないかと思って。当時、音楽雑誌の中でも人気のあった『スイング・ジャーナル』に読者論壇という誰でも投稿できるページがあって、そこに投稿したものが掲載されたことがきっかけで編集部から電報をいただきました。私の投稿原稿にたくさんファンレターが来たので、“本気で書いてみませんか?”と仰ってくださって、“喜んで書かせてください!”とお願いしたことからご注文をいただくようになったんです」
——音楽評論家として雑誌で原稿を書かれていくなかで、ラジオDJとしてもご活躍されています。
「“湯川さんはジャズだけでなくポップスもわかるからラジオのDJをやってください”と言われて、1960年からラジオも始めています。61〜62年くらいからラジオがどんどん多くなって、63年、東京オリンピックの前の年くらいにはDJとして人気が出ていました」
——ラジオに関しては、今と昔ではリスナーの方々の聞き方が全く違うのかなと。
「全然違うと思います。60年代の最初の頃は映画音楽が強くて、『エデンの東』は1950年代に、日本でその頃始まったラジオのコーナーで1位になると、1年半ほど1位が続いたんです。それだけ人気が落ちない。つまりレコードもまだ買えないとか、ラジオでしか聴けないという人たちがいっぱいいたと思います。それだけヒット曲の寿命が長かったんです。それが50年代だったと考えてください。外国から情報が入ってくるのが早くなり、種類も多くなり、レコード会社の中に洋楽専門の部署ができるようになったのが60年代で、その頃にはラジオも民放がたくさんできていました」
——ビートルズの人気に火がついたのも、その頃ですね。
「はい。1964年に、『抱きしめたい』という曲が日本に入ってきたのが2月でした。その年の4月には、アメリカのレコード業界誌である『ビルボード』で1位から5位までをビートルズが独占するんですね。“うわぁ、ビートルズってすごいんだ” って。だから次にビートルズが何を出すのか、というのを待ち構えていて。最初にビートルズの新曲を、誰がラジオでかけるかっていうのを、私たちDJやステーションが奪い合いをした…なんてことが始まるのは、ビートルズからでしたね」
ビートルズ来日公演の裏側
——ビートルズが来日された時の印象的なエピソードを教えてください。
「1964年にビートルズの人気が出てくると、翌年の65年には音楽雑誌の『ミュージック・ライフ』の編集長だった星加ルミ子さんが、日本から本物の刀を高額で手に入れて、ビートルズのマネージャーのブライアン・エプスタインに届けに行ってラインを作ったといわれています。それがきっかけで『ミュージック・ライフ』は、ビートルズの写真入りのグラビア記事を毎月出し始めて、どんどん売り上げを伸ばしていきました。ビートルズが日本に来た66年は、それから2年後です」
——その時に、湯川さんは何を担当されていたんですか?
「私はビートルズを招聘した読売新聞から来日特集号を頼まれました。しかしいざ日本にビートルズが来てみると、記者会見が1回あるだけ。私や星加さんはビートルズの現実的な情報提供者として2年の実績がありましたので、かろうじて記者会見には入れていただきましたけど、質問は一切できないんです。大新聞を中心とした記者クラブがすべて牛耳っていて、そこの代表記者質問だけだったんです」
——もどかしいですよね、畑違いの方が質問をして。
記者クラブで質問を出し合って“これを質問しよう”という、いわゆる公式質問という形で。それがめちゃくちゃおもしろくない質問だったんですよ。ビートルズにも適当にからかわれて。でもメディア側は、からかわれたのも分かっていなくて、そのまま記事にしたり。こちらは招聘元の新聞社なのに、ビートルズ側からも単独取材はできないといわれて、特集号に写真1枚撮れないとわかって。彼らを呼んだプロモーターの協同企画(後のキョードー東京)社長の永島達司さんに泣きついていたら、いきなり星加さんがビートルズに会いに行って写真を撮ったという情報が伝わってきたんです」
——星加さんは、どうやってビートルズに面会したんでしょうか?
「星加さんは、刀をブライアン・エプスタインに持って行った時に、もう1本持って行ったのを、広報担当のトニー・バロウという人にもプレゼントしていたんですね。それがあって、裏から『ミュージック・ライフ』にだけは連絡があったんです。私は当時『ミュージック・ライフ』の顧問をしていましたので、“『ミュージック・ライフ』は星加さんが絶対取材できるから大丈夫よね、じゃあ読売の方は私が頼まれたので私は読売で取材をします”と。“私の情報と星加さんの情報をお互いに共有できるようにしましょう”と約束をしていたんです。でも主催者の読売新聞が写真を撮れないということになったら、もうかっこつかないですよね。それで永島さんにお願いをしたら、ビートルズの武道館公演が終了して、明日日本から帰るという前の夜にビートルズの皆さんと私が食事をできるようにレストランを用意してくださったんです」
——ではいよいよ、ビートルズとの面会が実現できたんでしょうか?
「いいえ、その日に警視庁からビートルズに対して外出禁止令が出ちゃったんです。ビートルズが移動する時には全部首都高、高速道路を止めたり、機動隊までが出て、大変な警備態勢が敷かれているようでした。アメリカのドワイト・D・アイゼンハワー大統領が日本に来た場合の予行練習だったんじゃないか、と言われています。安保闘争などがあった頃でしたから」
——ビートルズの来日に反対する人たちもいたそうですね。
「そうなんです。当時は屋根があって1万人が入れる会場は武道館しかありませんでしたから、武道館を借りることになったのです。それが政治討論番組で“ビートルズだか何だか知らないが、百害あって一利ないような音楽に神聖な武道館を貸すなとか、ロックなんてのはロクなもんじゃない、若者に悪影響を与える”と、そういうことを政治評論家の方たちが番組で仰ったのね。それを受けて武道館の館長であった正力松太郎さんが“ビートルズに武道館を貸すのは止めます”と言われて。正力さんは読売新聞の社主でもありましたから現場はびっくりして。永島さんはすぐビートルズ側にも説明をしないといけないということで、ロンドンまで飛ばれました。でもブライアンには会わないで、そのまま他の仕事でニューヨークを回ってすぐ帰って来られたそうです」
——ビートルズ側に伝える気持ちはなかったんですね。
「伝える気持ちはまったくなかったみたいです。永島さんは帰国後に“キャンセルをしたら、出演料以上の損失が発生します、武道館以外の会場は無いから、2000人しか入れない会場に分散したら、武道館の5回分をするには、とんでもないギャラになり、とてもできません”というお話をしたら、正力さんが“わかった、やることにしよう”と」
——ビートルズが日本でライブができたのが、奇跡的なことだったんですね。
「本当に奇跡的でした。すごく嬉しかったですね。そんな騒動の中で、ビートルズの何がいいのか、ビートルズって何だ?といったインタビューとか対談でいろいろ聞かれたんですけど、実際にビートルズはまだ女の子にとってのアイドル・グループでしたから一般には全く浸透していなくて、一過性のものだと思われていたんですね。武道館でビートルズが演奏したのはたった35分間11曲ですけど、今聴いても優れた曲ばかりで、何よりも今では世界の名曲としてもっともカバーされている『イエスタデイ』も入っていたんです。私は“この歌の何が悪いのか?”と思う側にいたので、とても不可解な大騒動でしたが、こうしてビートルズが来た50年前くらいから、初めてポピュラー音楽が評論の対象になっていきました」
音楽が心と身体を救う
——湯川さんは音楽療法を啓蒙する活動も行われているそうですが、そのきっかけは?
「当時は毎年アメリカに行っていましたが、ビートルズが日本に来た6年後にアメリカに行ったときに、“サンフランシスコで音楽療法のセッションがあるので、見たくありませんか?”と言われて見学に行ったら、音楽療法士の方が自閉症の子供とセッションをしていました。時々奇声を発している男の子にドラムを叩かせていて、その子はグルグル回ってドラムを叩いては、またグルグル回って、だんだん沈静化していくんです。ピアノを弾いている先生とその子のドラムが会話でもするようになっていって、やがて疲れて座ったところで“何か飲みたい?”って聞かれたら“うん” って言って飲んだりする。そういうセッションを見せてもらって、はじめて音楽療法というものがあることを知りました」

——その光景が湯川さんにとっては、衝撃的だったんですね。
「日本に帰ってきてから音楽療法の本を探したら、音楽之友社から『音楽療法』という本が出ていたんです。その本を買って、それから音楽療法の勉強をするようになりました。私は今、日本音楽療法学会の理事をやっていますけど、音楽というのはいろんなエレメントがあって、人間の心や体や脳に働きかけるんです。今から25年くらい前に、校内暴力とか家庭内暴力が問題になった時代がありましたが、そんな頃に、校内暴力がものすごかった高校が、ブラスバンドを作って、みんなでブラスバンドをやるようになったら暴力がおさまったといったことが話題になったりしました」
——最近ではダンスが必修科目にもなっていますよね。
「あれはブラスバンドが盛んになって、バンド活動が始まるようになったのと同時くらいに、北海道からソーラン節を踊るというのが、本土にどんどん入ってきた頃があったんですね。みんながソーラン節を踊ることで、校内暴力が減ったといわれています。音楽療法でわかったんですけど、若者の鬱積したエネルギーって、激しい音楽を聴いたり太鼓を叩くことで全部発散しちゃって、沈静化するのね。それで初めて人の言葉に耳を傾けるようになったり。こういったことを見つけてくれたのは、16世紀のヨーロッパのお医者さんで、うつ病の患者さんに音楽を選ばせると、陰々滅々とした音楽を選んで、それを聴きながらメソメソ泣いたりしているうちに、少しずつ明るい音楽を聴けるようになっていく。明るい音楽を聴いて、いいねって言えるようになっていく。その逆がすごく荒れて、暴力的に、誰も俺なんて理解してくれない、生きてるのも嫌だと言っているような怒りに満ちた子供達に音楽を選ばせると、もうギンギンガンガンのヘヴィメタルとかを選ぶ。そこでヘッドバンギングをしたりしながら聴いてると、沈静化していくという現象が起きるわけです」
——その時に聴きたい音楽が、人間の心理を表しているんですね。
「それを音楽療法の世界では“同質の原理”と言っていますが、うつ病の患者さんに、そんなくよくよしてないで踊りに行こうよとか、遊びに行こうとか言っても、逆に苦痛になっちゃったりするから、うつ病の患者さんに“頑張れって言ってはいけない”というじゃないですか。昔は頑張れって言ってたんですよね。でも今は“頑張れって言うな”と。それと同じことが音楽療法の世界ではずっと言われてきていて、その人が選ぶ音楽がその人にとっての名曲なんです。そこには必ず、ゆらぎのリズムがあって、リズムが外から与えられることで、人は感応して自分の心臓というリズム楽器が整う、という力があるんですね。外から一定のリズムを与えられると、左脳的にくよくよ考えていたことが右脳に置き換えられていったり、その人にとってのもっとも生理的に望ましい基本リズムが整うという作用が起こるんです。そして、交感神経と副交感神経のサーモスタットがうまく働くようになって、自律神経失調症が治るというのも、リズムの秘密なんです。それがわかってきたのが音楽療法の世界で、だからいかに音楽を人に与えることで、どういう生理的な反応が起きるかなんですけど。その人が聴いて気持ちのいい音楽が、その人にとっての名曲なんですね」
——とても素敵なお話ですね。この音楽療法って、実際にどんな場所でやられていますか?
「今いちばんニーズがあるのが老人介護の施設なんです。ビートルズ来日から約50年ですから、当時20歳だった人も、もう70歳。老人ホームに入っている人もいるので、前は音楽セラピーというと、『赤とんぼ』とか、『ふるさと』だったんですけれど、それではあまり嬉しくないという老人も増えていらっしゃるようです」
——今の時代は、本当に多種多様ですね。
「ずいぶん変わってきていますね。一緒に体を動かしたり、一緒に歌ったり、動きにくい体がリズムを与えられることで活性化していきます。一昨年くらいに『パーソナル・ソング』という映画がアメリカから入ってきて随分評判になったんですけど、自分が思春期の一番楽しかった頃に聴いていた音楽を聴かせるだけで、記憶が蘇っちゃったりするんですね」
——音楽はすごいパワーを秘めているんですね。
「私の体験として母が88歳になった時に、私の顔も名前もわからなくなっちゃって、“愛情って何なんだろう”と考えました。私のために命がけで生きてくれた人なのに…と思った時に、母の子供の頃の歌を歌うと、全部歌詞が出てくるんです、そして最後まで嬉しそうに歌うんです。私の記憶よりも音楽は深くに入ってるんだと。それは私にとってものすごい体験になりましたね」
——最後にお伺いしたいのですが、人々にとって音楽はどんな存在であってほしいですか。
「今、本当に好きな音楽を好きな環境で聴ける国がこの世界にはどのくらいあるか。考えていただければわかると思うんですけど、シリアの子どもたちがいくら音楽を聴きたくたって、住む場所さえないじゃないですか。難民キャンプだってそうでしょう?そういう風に考えると、私たちは本当にラッキーなところに生きていると思うんです。そのことを認識して、そういう環境を絶対に失くさないでほしい。宝物だと思ってほしいです」
湯川れい子さんの写真館



PROFILE
湯川れい子 | 東京都生まれ、山形県米沢市で育つ。昭和35年、ジャズ専門誌『スウィング・ジャーナル』からジャズ評論家としてデビュー。早くからエルヴィス・プレスリーやビートルズを日本に広め、作詞家としても活躍。代表的なヒット曲に『涙の太陽』『ランナウェイ』『センチメンタル・ジャーニー』『六本木心中』『恋に落ちて』など多数。1972年頃より音楽療法にも関心を深め、活発に活動している、また、環境問題や次世代の子供たちの育成にも力を注いでいる。